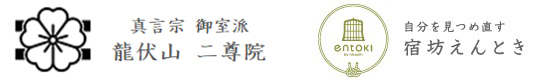葬儀について

1.どなたのお葬式も承ります
二尊院では、これまでお付き合いのない新規の方の葬儀や、葬儀のみをご希望の方のご依頼も承ります。もちろん四十九日や納骨など、その後のご供養も責任をもって承ります。過去の宗旨宗派、国籍、性別などは一切不問で、真言宗の法式に則って奉修いたします。
火葬にはしてあるが、まだ葬儀をしていないので、葬儀(骨葬)を希望される方も対応いたします。
もともと、祈祷寺院ですので檀家制度を施いていません。「来るもの拒まず、去る者追わず」の精神で自由なお寺とのお付き合いをお願いいたしています。
2.葬儀費用(お布施)について
お布施に決まりはありませんが、目安として二尊院の場合ご戒名を含め、一般的な葬儀(枕経、お通夜、葬儀、戒名料)で20万円程度包まれる方が多いです。経済的な事情がある方は、分割などご相談にのりますので安心して二尊院をお頼りください。
3.葬儀の前にすべきこと(和尚からのアドバイス)
喪主や遺族として葬儀を行うとなると、さまざまな準備が必要です。私も祖母、父の葬儀を取り仕切りましたが、たった12時間程度でたくさんのことを決めていかなければなりません。正直何が何だか分からなくなったりもします。
今回は、葬儀がはじまるまでに必要な準備を私の経験を踏まえてまとめてみました。まずは事前にシュミレーションしておきましょう。
元気な時から葬儀をポジティブに考える

-
事前準備をする
「葬儀=死」ですから、ネガティブに考えてしまうと思います。ただ、これまでに人生の中で、いろんな節目があり、その都度お祝いなどイベントを行ってきて、最後の最後、この世で行う総仕上げが葬儀です。
子供たちには、迷惑を掛けたくないから質素なお葬式、家族葬でいいと故人は言っていたけれども、どんなイメージだろうか??葬儀にはいろんなプランやオプションがあり、棺桶や骨壺ひとつ選ぶだけでも、いっぱい種類があるのです。あとは任せるという感じだと、家族はとても悩むところでもあります。
なので、お願いする葬儀社は、本人自身が決めて、ある程度イメージするプランの見積もりを取っておくと、予算を立てやすいですし残された家族は希望通りに見送ってあげようと思うはずです。葬儀社の雰囲気や立地、担当者の人柄や費用面に至るまで、様々ですので何件か見て歩きましょう。
-
預貯金をおろす
本人の死亡後、本人名義の銀行口座は凍結されます。葬儀費用を本人の預貯金から工面する予定であれば、早めに現金をおろしておきましょう。和尚は祖母の葬儀の時、このことを知らず苦労しました。凍結後にお金をおろす場合は、金融機関によるとは思いますが専用の様式に、すべての相続人のサインと押印が必要になるので、それなりの時間を要します。
ついに危篤状態になったとき

-
会わせたい人に連絡する
病院などで、医師から危篤を告げられたら、家族や親族、親しい友人などに連絡しましょう。遺言やエンディングノートなどに意思表示が書かれている場合には、内容に沿って行動します。連絡は、電話で行うのが一般的です。
-
しっかりお別れをする
ご臨終間際でも、耳だけは最後まで聞こえているといいます。手を握ったりして側に付いて話しかけてあげましょう。
臨終の宣告後、葬儀までに行うこと

-
葬儀社を手配する
ご臨終を迎えたら、葬儀社へご連絡ください。葬儀社には「二尊院に葬儀をお願いしたい」旨をお伝えください。決まった葬儀社がない場合、長門市内でしたら良心的で誠実な葬儀社をご紹介いたしますので、お尋ねください。一般的に葬儀社が決まると、行政手続きに必要な書類手続き(死亡届の提出、火葬許可証の申請準備)を代行してくれます。
-
安置
速やかに病院や施設から寝台車で搬送し、葬儀会館やご自宅にご安置いたします。(和尚の個人的な意見としては、入院中ご自宅に帰りたくても帰れなかったケースが多いと思います。通夜までの間だけでも自宅に連れて帰ってあげて欲しいなと思います。)
-
喪主と役割りを決める
喪主だけでは、やることが多すぎるので、連絡係、食事係、接客係、受付係などを決めて分担して対応しましょう。(例:参列者に日程を知らせる。お布施や会葬礼状、返礼品の手配。料理や茶菓子の手配。火葬場への同行者数を確認。電報や供花の順番など)
-
葬儀について故人の遺志があるか確認
どんな葬儀を行うかについては、遺族の希望だけでなく、故人の遺志を尊重することも大切です。故人がエンディングノートを残している場合は、何か希望が書かれていないか確認しましょう。
-
枕経
亡くなった人の枕元で読経する仏教の儀式です。冥途への旅立を促すとともに、故人の心を安心させるために行われる旅の道しるべともされています。その後、ご家族・ お寺・葬儀社の三者で通夜や葬儀の日程を決定します。
-
通夜
通夜法要を行います。僧侶の読経後に法話、法要後に喪主(親族)挨拶、弔問客の見送り、通夜振舞い等を行います。ご家族のみで通夜を行うこともあります。通夜とは元来、夜通しロウソクや線香を絶やさずに一晩中故人に寄り添い、偲び、静かに思い出を語り合い、最期の別れを惜しむものです。
-
本葬
葬儀を行います。僧侶による引導作法および読経、弔辞、弔電披露、喪主(親族)挨拶、焼香、送り花(お別れ)、葬列先導のもと霊柩車乗棺、火葬場へ向けて霊柩車での出棺等を行います
-
火葬
式場から火葬場へ到着したら、炉前ホールで読経いたします。いよいよ最後のお別れです。火葬後に収骨(お骨上げ)を行います。ご遺骨はご遺族の皆様方の手で骨壺に収められます。なお、地域によっては、火葬の後に本葬を行うこともあります。
-
初七日忌
お亡くなりになってから七日目に行う法要が初七日法要ですが、最近では、遠方のご親族が多い、縁故の方を度々煩わせるのは心苦しいなど、さまざまな理由から葬儀と共に行うことが一般的です。満中陰(四十九日)の日程、お位牌・お仏壇、お墓・納骨についてなど、お葬式が終わってからのことに関するご相談も承ります。
お問い合わせフォーム
葬儀に関するお問い合わせは、以下のリンク先からご連絡ください。